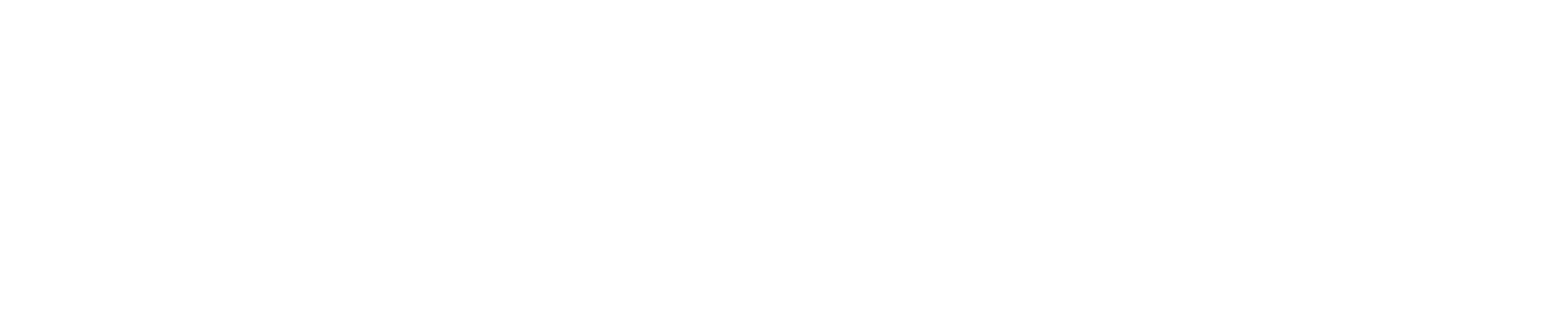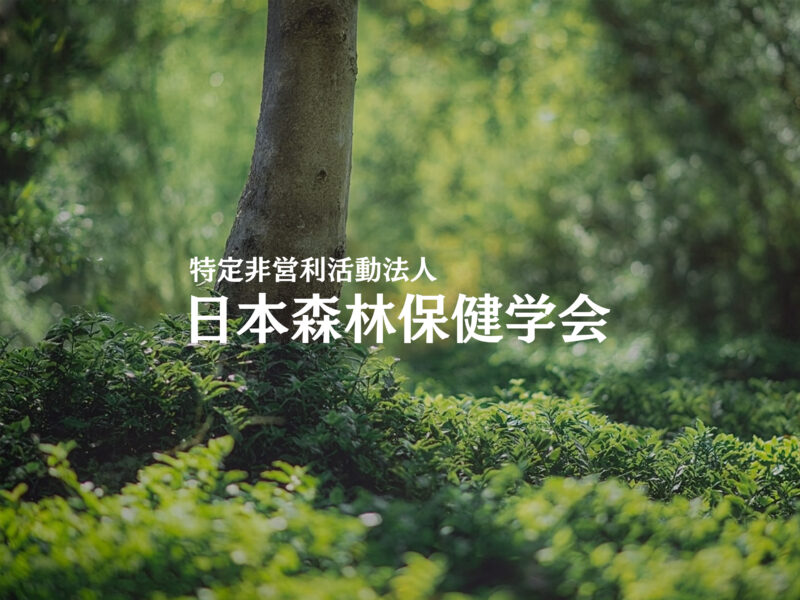「森林と健康 シンポジウム」盛況に開催されました!
6月22日(土)午後1時半より、東京農業大学・横井講堂において、日本森林保健学会、東京農業大学、森林文化協会の合同主催による、「森林と健康シンポジウム」が盛況に開催されました。 日本森林保健学会創設10周年を記念してのシ […]
第8回学術総会&研修会が開催されました
8回目の学術総会が、今年も東京農業大学を会場に開催されました。 はじめに、今年の基調講演は、「森林と文化」をテーマに、東京農業大学大学院 林学専攻 宮林茂幸教授にお話をいただきました。森林と人をつなぐことによって、コミュ […]
森林と人間の健康を考える国際会議が台湾で開催されました
森林と人間の健康を考える国際会議、「森林療癒 國際研討會 2017 International Conference of Forest Human Health and Well-being 2017」が、2017年1 […]
第7回学術総会&研修会が盛況に開催されました
6月24日(土)、今年も東京農業大学を会場に、第7回目の日本森林保健学会が開かれました。 今年は、クマ研究の第一人者である、森林生態学研究室の山﨑晃司教授に、クマについての基調講演をいただき、その後、6件の会員発表が行わ […]
第6回学術総会、研修会が開催されました
第6回目となる学術総会が、6月18日(土)に今年も東京農業大学・世田谷キャンパスで開かれ、 翌19日(日)には、国分寺崖線での研修会が行われました。 今年のテーマは、「現代人のエスケープの場としての森林」。 人口の大半が […]
第5回学術総会、研修会が無事に終了しました!
6月27日(土)13時より、東京農業大学・世田谷キャンパスにて、今年の学術総会が開催されました。 今年のテーマは、「森林の健康=人間の健康!?」。基調講演をはじめ、様々な研究発表を通して、森林と人間の健康のつながりについ […]
第4回目の学術総会が無事に終了いたしました!
第4回目の日本森林保健学会が、 6月14日(土):東京農業大学・世田谷キャンパス 6月15日(日):青梅の森 で行われ、盛会に終了いたしました。 今年のテーマは、「森林と人間をつなぐ精神(こころ)」。 14日(土)には、 […]
2013年NPO法人北海道森林療法研究会シンポジウム(終了)
2013年NPO法人北海道森林療法研究会シンポジウム 「森林環境を活用した健康づくり町づくり」 日時:2013年10月12日(土)~13日(日) 場所:東川町農村環境改善センター(参加無料) 主催: NPO 法人北海道森 […]
第3回 学術総会が開催されました!
日本森林保健学会の第3回目の学術総会が、6月22日(土)に、東京農業大学・世田谷キャンパスで開催され、今回も北海道から山陰地方まで、全国の方が集まりました。
【6/22開催】第3回 日本森林保健学会 学術総会
今月は、日本森林保健学会の学術総会が下記の通り開かれます。 どうぞふるってご参加ください! 第3回 日本森林保健学会 学術総会 ◆日 時:2013年6月22日(土)13:00~ ◆場 所:東京農業大学・世田谷キャンパス […]