新着情報:information 一覧
森と人の文化誌『Green Power グリーン・パワー』(2020 3月号)
森と人の文化誌『Green Power グリーン・パワー』(2020 1月号~12月号)に、“森林アメニティのすすめ”が特集され、日本森林保健学会理事長・理事・会員の記事が掲載されました。
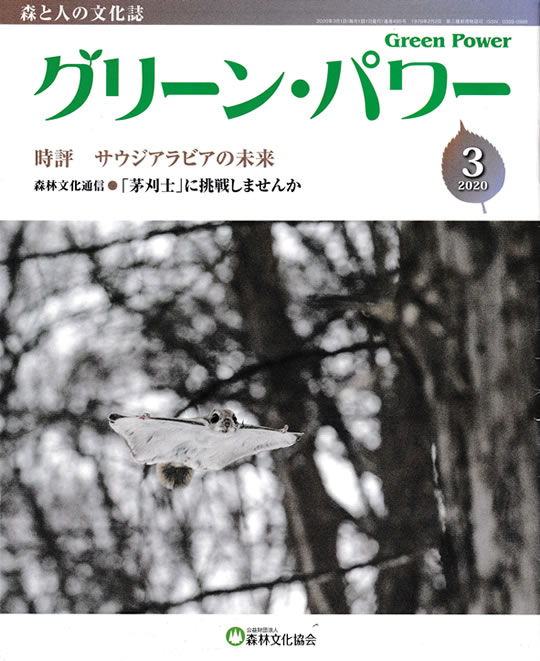
2020 3月号 p8-9 ―“森林アメニティのすすめ” 私たちの健康と森林―
第3回 「森林浴の科学① 森林と心身の回復力」
(国研)森林機構 森林総合研究所 ダイバーシティ推進室長 高山 範理
森と人の文化誌『Green Power グリーン・パワー』(2020 2月号)
森と人の文化誌『Green Power グリーン・パワー』(2020 1月号~12月号)に、“森林アメニティのすすめ”が特集され、日本森林保健学会理事長・理事・会員の記事が掲載されました。
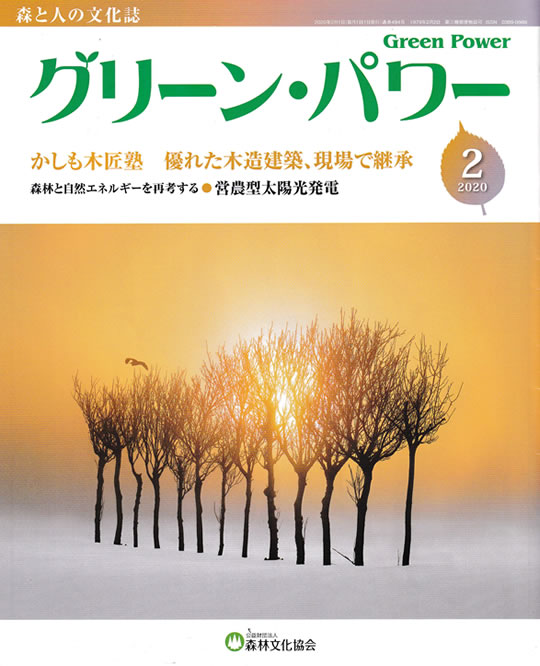
2020 2月号 p8-9 ―“森林アメニティのすすめ” 私たちの健康と森林―
第2回 「地域病院の事例 社会福祉施設の事例」
日本森林保健学会理事長・東京農業大学教授 上原 巌
森と人の文化誌『Green Power グリーン・パワー』(2020 1月号)
森と人の文化誌『Green Power グリーン・パワー』(2020 1月号~12月号)に、“森林アメニティのすすめ”が特集され、日本森林保健学会理事長・理事・会員の記事が掲載されました。
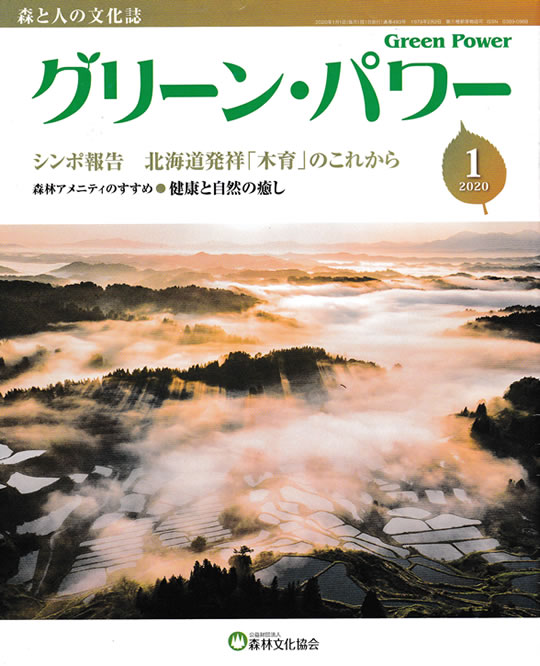
2020 1月号 p8-9 ―“森林アメニティのすすめ” 私たちの健康と森林―
第1回「検討と自然の癒し その表裏一体の流行」
日本森林保健学会理事長・東京農業大学教授 上原 巌
樹木の花を見たことはありますか?
カレンダーは7月に入り、夏の到来ですね!
今年の夏は暑くなるでしょうか? それとも冷夏でしょうか?
ところで、みなさんは、樹木の花を見たことはありますか?
お花と言えば、生け花や草花の花がすぐに思い浮かぶところです。
でも、もちろん樹木にも花があります。
写真は、ムラサキシキブの花です。
ひまわりやショウブのような大きな花ではありませんが、可愛らしい花ですね。
秋になると、この花びらの色そのままの紫の果実が実ります。

しかしながら、こんなに小さな花を見ている人はいるのでしょうか?
はい、もちろんいます。それはあなたですね(笑)。
そして、人間以外では、鳥や虫がこの花を見ています。
次の写真は、アカメガシワの花です。
甲虫が早速とりついているのがわかりますか?
体全体で花を観賞し、香りをかぎ、蜜を楽しんでいるようです。

夏に咲く樹木の花を見つけてみてくださいね。
日本森林保健学会 第11回学術総会および会員総会オンライン開催のお知らせ
<学術総会にご出席される皆様へ>
6月20日に、ZOOMのご案内を学会事務局からメールで送信いたしました。案内のメールを受け取ってない場合は、事務局(info@forest-and-human-health.jp)にご連絡ください。よろしくお願いいたします。
- 第11回学術総会・会員総会:2021年6月26日(土) オンライン(ZOOM)
- 第11回学術総会・研修会:2021年6月27日(日)成城三丁目緑地 雨天中止
10:00集合 @東京農業大学世田谷キャンパス(※会員限定)
<内容>
(1) 基調講演 13:00~13:45
「森林浴とエビデンス-その拡がりと終着-」 高山範理
(当学会理事/森林総合研究所 上席研究員)
(2) 会員発表 14:00~15:30(一人15分 発表12分、質疑応答3分)
- 「森・樹木とともに生きるよろこび 「森に近い生活」の提言」
近森 聡(関西大学) - 「地域住民の森林との関わりの実態と地域の特性 —山梨県山中湖村におけるアンケート調査から—」
齋藤暖生1・藤原章雄1・竹内啓恵2・森田えみ3・高山範理3(1東京大学演習林、2樹づ木合同会社、3国立研究開発法人森林総合研究所) - 「放置里山林の再生と森林保健活動の両立をめざして〔中間報告その2〕~大分県のある社会福祉法人の森林保健活動への可能性の模索~」
杉浦嘉雄(国東半島・宇佐GIAHS専門家会議 委員) - 「福島県相馬地方の森林環境における放射性降下物質の動態—東京農大・東日本支援プロジェクト—」
上原 巌(東京農業大学地域環境科学部)
(3) 会員総会 15:45~16:00
- 会員の参加費用は、無料です。NewsLetterでご案内した出欠フォームへ5月31日(月)17時までにご連絡ください。
⇒会員発表の申込は締め切りました。ご出欠のご返信がまだの方は、ご出欠フォームへのご連絡、または直接事務局へご連絡いただけますようお願い申し上げます。 - 発表予定者は、発表題目・要旨を6月7日(月)17時までに事務局宛(事務局宛(info@forest-and-human-health.jp)にご提出ください。
- 非会員の参加費用(聴講のみ)は、3000円です。学生は事務局までお問合せください。
非会員は、学術総会の発表および研修会へのご参加ができませんので、ご了承お願いいたします。
<参加申込方法>
件名を「第11回学術総会参加希望」とご記載され、(1)お名前(フリガナ)、(2)ご所属先名、(3)職位、(4)メールアドレスをご記入いただき、事務局宛(info@forest-and-human-health.jp)に5月31日(月)までにお送りください。




