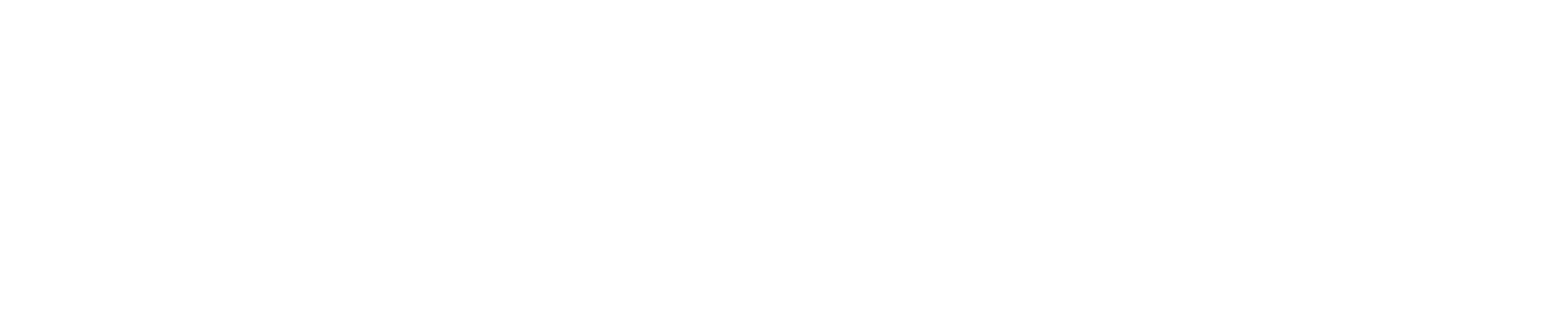謹賀新年 2026年 令和8年
みなさま あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりました。 今年の学術総会は、6月に大阪でおこなわれます。昨年は、福岡、福井、福島などいずれも「福」のつく県の森林に行脚いたしましたが、本年も各地におうかが […]
インフルエンザ、コロナにお気をつけください!
今年もとうとう師走、12月になりました。 みなさまいかがおすごしでしょうか? さて、私はこの度、インフルエンザA型にかかりました。 発熱、悪寒、節々の痛み、咳、吐き気など、典型的な症状に数日間見舞われました。 けれども、 […]
森林のアメニティはすみずみまで
暦は10月。学びの秋に入りましたね。 小生が勤務する東京農業大学では、「森林アメニティ学」という科目があります。後期の新学期が始まり、最初の講義では、こんなレポート課題を出しました。「林地では、間伐後の伐根の散乱が見られ […]
ガールズ・スクールでの出前講義
みなさま、残暑お見舞い申し上げます。 連日の猛暑のおり、関東の女子校に出かけてまいりました。 夏休み中の、しかも自由参加にもかかわらず、110名ものみなさんが集まってくれました。 今どきの多感な時代であっても、樹木、香り […]
第15回 学術総会が大分県別府市で開催されました
本年度の日本森林保健学会の学術総会が、6月28日(土)、大分県別府市の国際会議場(ビーコンプラザ)にて開催されました。 大会長は、杉浦嘉雄先生。団体会員である日本造園修景協会大分県支部のみなさまには、事前のご準備から当日 […]
ぼちぼち森林に行ってみませんか?
5月31日(土)新宿の会場にて、対面とオンラインのハイブリッド開催で公開セミナーが開催されました。今回のテーマは、「ぼちぼち森林に行ってみませんか! ~障がい者・高齢者のための森林空間利用最前線 ~」。 日本森林保健学会 […]
都会のシークレット・ガーデン
今年の連休、いかがお過ごしでしょうか? わたしは、今春3月にオープンし、今月10日(土)にお話会と散策会をおこなう、東京・世田谷の桜新町にあるブックカフェに出かけてきました。カフェには様々な古本が集まり、わたしの本も何冊 […]
今年はワークショップの年になります
この3月は、福岡県八女市、福井県越前町でワークショップをおこないました。ともに地域の森林に出かけ、地域のみなさまと交流をし、地域の森林と人間の健康を考えました。 ワークショップの内容は、 ① その地域の森林はどのような森 […]